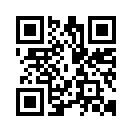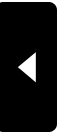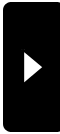2007年05月07日
★新渡戸稲造の武士道
約10年前、著名なベルギーの法学者、
故ラヴレー氏の家で歓待を受けて数日を過ごした。
ある日の散策中、私たちの会話が宗教の話題に及んだ。
「あなたがたの学校では宗教教育をいうものがない、とおっしゃるのですか」
とこの高名な学者が訪ねられた。
私が「ありません」という返事をすると
氏は驚きのあまり突然歩みを止められた。そして忘れがたい声で
「宗教がないとは、いったいどうやって子孫に道徳を授けるのですか?」
と繰り返された。
その時、私は愕然とした。
なぜなら、私が幼いころ学んだ人の道は
学校で受けたものではなかったからだ…
そこで私に善悪の観念をつくりださせた様々な要素を分析すると
そのような観念を吹き込んだものは
「武士道」であることがようやくわかった。
-------------------------------------------------
だいぶ前の話だが、中国から留学している娘さんと
たまたま仕事で一緒になることがあった。
彼女は卒業論文で日本の特徴を書くことに決めたらしいが
その題材を「武士道」にすると言うのだ。
彼女が言うには
「日本人はみんな優しく真面目で信頼できる。中国では、そんなことはない。その根本的な違いは、武士道にあると思えるんです」
私は、何も言えなかった。
そう言えば、そんなこと意識してなかったと思いました。
いつのまにか根づいていた、武士道。
もう一度、この精神を勉強しなければならない
時代が到来したような気がする。
新渡戸 稲造
(にとべ いなぞう、文久2年8月8日(1862年9月1日) - 1933年10月15日)は、農学者、教育者。国際連盟事務次長も務め、著書 Bushido: The Soul of Japan(『武士道』)は、流麗な英文で書かれ、名著と言われている。日本銀行券のD五千円券の肖像としても知られる。札幌農学校(現在の北海道大学)の二期生として入学する。農学校創立時に副校長(事実上の校長)として一年契約で赴任した、「少年よ大志を抱け」の名言で有名なウィリアム・S・クラーク博士はすでに米国へ帰国しており、新渡戸たちの二期生とは入れ違いであった。 祖父達同様かなり熱い硬骨漢であった。ある日の事、学校の食堂に張り紙が貼られ、「右の者、学費滞納に付き可及速やかに学費を払うべし」として、稲造の名前があった。その時稲造は「俺の生き方をこんな紙切れで決められてたまるか」と叫び、衆目の前にも関わらず、その紙を破り捨ててしまい、退学の一歩手前まで追い詰められるが、友人達の必死の嘆願により何とか退学は免れる。他にも教授と論争になれば熱くなって殴り合いになることもあり、「アクチブ」(アクティブ=活動家、今で言うテロリストの意味合いもある)というあだ名を付けられた
東京帝国大学進学後、「太平洋のかけ橋」になりたいと私費でアメリカに留学、ジョンズ・ホプキンス大学に入学。この頃までに稲造は伝統的なキリスト教信仰に懐疑的になっており、クエーカー派の集会に通い始め正式に会員となった。クェーカーたちとの親交を通して後に妻となるメリー・エルキントンと出会った。
その後札幌農学校助教授に任命され、ジョンズ・ホプキンスを中途退学して官費でドイツへ留学。ボン大学などで聴講した後ハレ大学より博士号を得て帰国し、教授として札幌農学校に赴任する。この間、新渡戸の最初の著作『日米通交史』がジョンズ・ホプキンス大学から出版され、同校より名誉学士号を得た。だが、札幌時代に夫婦とも体調を崩し、カリフォルニアで転地療養。この間に名著『武士道』を英文で書きあげた。日清戦争の勝利などで日本および日本人に対する関心が高まっていた時期であり、1900年に『武士道』の初版が刊行されると、やがて各国語に訳されベストセラーとなった。
故ラヴレー氏の家で歓待を受けて数日を過ごした。
ある日の散策中、私たちの会話が宗教の話題に及んだ。
「あなたがたの学校では宗教教育をいうものがない、とおっしゃるのですか」
とこの高名な学者が訪ねられた。
私が「ありません」という返事をすると
氏は驚きのあまり突然歩みを止められた。そして忘れがたい声で
「宗教がないとは、いったいどうやって子孫に道徳を授けるのですか?」
と繰り返された。
その時、私は愕然とした。
なぜなら、私が幼いころ学んだ人の道は
学校で受けたものではなかったからだ…
そこで私に善悪の観念をつくりださせた様々な要素を分析すると
そのような観念を吹き込んだものは
「武士道」であることがようやくわかった。
-------------------------------------------------
だいぶ前の話だが、中国から留学している娘さんと
たまたま仕事で一緒になることがあった。
彼女は卒業論文で日本の特徴を書くことに決めたらしいが
その題材を「武士道」にすると言うのだ。
彼女が言うには
「日本人はみんな優しく真面目で信頼できる。中国では、そんなことはない。その根本的な違いは、武士道にあると思えるんです」
私は、何も言えなかった。
そう言えば、そんなこと意識してなかったと思いました。
いつのまにか根づいていた、武士道。
もう一度、この精神を勉強しなければならない
時代が到来したような気がする。
新渡戸 稲造
(にとべ いなぞう、文久2年8月8日(1862年9月1日) - 1933年10月15日)は、農学者、教育者。国際連盟事務次長も務め、著書 Bushido: The Soul of Japan(『武士道』)は、流麗な英文で書かれ、名著と言われている。日本銀行券のD五千円券の肖像としても知られる。札幌農学校(現在の北海道大学)の二期生として入学する。農学校創立時に副校長(事実上の校長)として一年契約で赴任した、「少年よ大志を抱け」の名言で有名なウィリアム・S・クラーク博士はすでに米国へ帰国しており、新渡戸たちの二期生とは入れ違いであった。 祖父達同様かなり熱い硬骨漢であった。ある日の事、学校の食堂に張り紙が貼られ、「右の者、学費滞納に付き可及速やかに学費を払うべし」として、稲造の名前があった。その時稲造は「俺の生き方をこんな紙切れで決められてたまるか」と叫び、衆目の前にも関わらず、その紙を破り捨ててしまい、退学の一歩手前まで追い詰められるが、友人達の必死の嘆願により何とか退学は免れる。他にも教授と論争になれば熱くなって殴り合いになることもあり、「アクチブ」(アクティブ=活動家、今で言うテロリストの意味合いもある)というあだ名を付けられた
東京帝国大学進学後、「太平洋のかけ橋」になりたいと私費でアメリカに留学、ジョンズ・ホプキンス大学に入学。この頃までに稲造は伝統的なキリスト教信仰に懐疑的になっており、クエーカー派の集会に通い始め正式に会員となった。クェーカーたちとの親交を通して後に妻となるメリー・エルキントンと出会った。
その後札幌農学校助教授に任命され、ジョンズ・ホプキンスを中途退学して官費でドイツへ留学。ボン大学などで聴講した後ハレ大学より博士号を得て帰国し、教授として札幌農学校に赴任する。この間、新渡戸の最初の著作『日米通交史』がジョンズ・ホプキンス大学から出版され、同校より名誉学士号を得た。だが、札幌時代に夫婦とも体調を崩し、カリフォルニアで転地療養。この間に名著『武士道』を英文で書きあげた。日清戦争の勝利などで日本および日本人に対する関心が高まっていた時期であり、1900年に『武士道』の初版が刊行されると、やがて各国語に訳されベストセラーとなった。
Posted by 遠州ナビ山下隆宏 at 09:34│Comments(0)